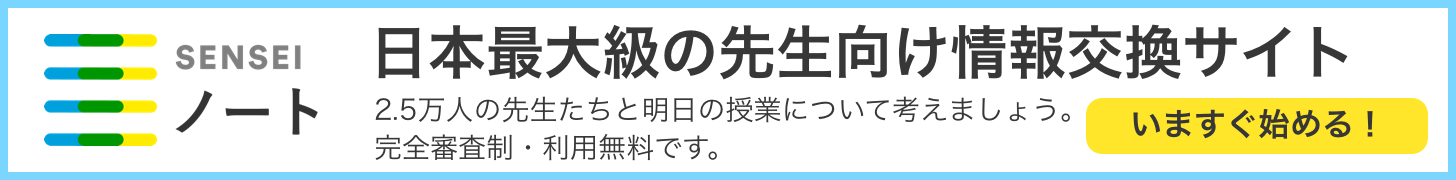| 開催日時 | 09:30 〜 16:00 |
| 定員 | 6名 |
| 会費 | 15,000円 |
| 場所 | その他オンライン(ZOOM) |
このイベントは終了しました
気になるリストに追加
進路相談や生徒指導で、職員室や会議で、保護者や地域住民への対応で・・・こんな経験ありませんか?
-「困っていることはない?」「〇〇は大丈夫?」と質問しても、「大丈夫です」と言われ、その先が続かない
-「ミーティング(面談・会議)に参加してください」と、何度も言わないと保護者・生徒・同僚などが集まらない
-言葉ではやる気を見せるが、実際には動かない人への対応に時間をとられる
-相手から「もっと〇〇があれば」「〇〇が足りない」「こういうサポートがあったらよかったのに」という言葉がよく出る
-議論の最後には「文科省が悪い」「教育委員会がこうこうだから・・・」「教員(生徒・保護者)ひとりひとりの意識の変化が・・・」と大きな話になってしまい、具体的なアクションに結びつかない
・・・これでは、個人やクラス・学校・家族のホントの課題に迫り、本人を課題解決に乗り出そうという気にさせることはできません。
実は、こうした状況の原因は、相手とのコミュニケーション方法にありました。
このような「あるある」シチュエーションをひっくりかえし、本音のやり取りをするには、どういう会話をすればいいのでしょう?
地域づくりの活動現場で生み出された「メタファシリテーション」は、超シンプルな質問を組み立てていく対話術です。
基礎講座では、この手法を座学と実践練習で一日かけてしっかり身に付けます!
小手先のテクニックや知識ではない、コミュニケーションの本質にせまる実践的な内容と終了後のフォローアップで、修了生の仕事・活動・日常生活に確実に変化をもたらす研修として、各地で好評を博しています。
◆講座の詳細・お問い合わせ・お申し込み http://muranomirai.org/trgbasic
(定員に達し次第、お申し込みの受付を終了いたします。)
◆こんな方におすすめ
・教育関係者や子育て中の方で、子どもとのコミュニケーションを改善したい方
・研修や授業の企画・組み立てやスタッフ育成・人材育成プログラムを担当されている方
・福祉関係のお仕事で、対人支援スタッフの支援や人材育成を担当されている方
・NPO/ボランティアセンター/公的機関で相談窓口を担当されている方
・国内外の地域コミュニティづくりに携わっている方
・青年海外協力隊や地域おこし協力隊に赴任予定/応募予定の方
◆開催概要
ZOOMというウェブ会議サービスを使って、ご自宅(またはご自身のオフィスなど)で参加して頂けるオンライン講座です。
下記のご準備が必要です。
1 インターネットに接続できるパソコン
2 パソコンに内蔵または外付けのウェブカメラ(画像のやり取りができる状態)
3 パソコンに内蔵または外付けのマイク・スピーカー・ヘッドフォン等(音声のやり取りができる状態)
5時間の講座を前半・後半に分けて実施します。下記の日程から、前半1つ・後半1つずつ日程を選んでお申し込みください。(できるだけ同じ講師による日程を選択してください)
ステップ1 前半
日時:2018年12月11日(火) 9時半から12時
日時:2018年12月13日(木) 20時から22時半
日時:2018年12月16日(日) 13時半から16時
ステップ1 後半
日時:2018年12月19日(水) 9時半から12時
日時:2018年12月20日(木) 20時から22時半
日時:2018年12月23日(日) 13時半から16時
◆メタファシリテーションを使った対話の事例
「自分のことは自分でやる」子になる対話って?
http://somneedwest.blogspot.jp/2016/09/blog-post_45.html
高校でのメタファシリテーション
http://somneedwest.blogspot.jp/2017/03/blog-post_28.html
進路に悩める友人にかける言葉
http://somneedwest.blogspot.jp/2017/02/blog-post.html
弟からの思いもよらない返事
http://somneedwest.blogspot.jp/2017/01/blog-post_31.html
「メタファシリテーション(対話型ファシリテーション)ファシリテーション自主学習ブログ」より
http://somneedwest.blogspot.jp/
イベントを探す
関連する人気のセミナー・研究会・勉強会
ファシリテーションのセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す