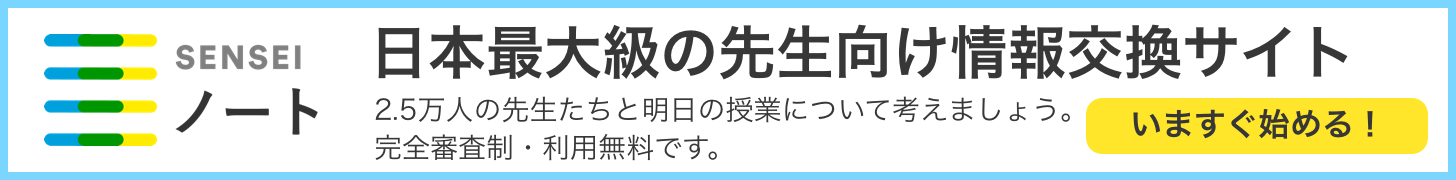終了
中止/延期【子どもの通訳? 子どものマイク? 木村泰子さんと語りあう!子どもアドボカシー文化ってなんだろう?】対談型おはなし会 木村泰子とアンドウジュン
| 開催日時 | 13:30 〜 15:30 |
| 定員 | 150名 |
| 会費 | 2000円 |
| 場所 | 愛知県豊田市若宮町1丁目57番地1 A館T-FACE 9階(松坂屋上階) |
このイベントは終了しました
気になるリストに追加
本イベントは中止/延期となりました。
【中止 / 延期のお知らせ】
下記イベントについて、主催者より重要なお知らせをさせていただきます。
*イベント名:『子どもの通訳?子どものマイク?木村泰子さんと語りあう!子どもアドボカシー(advocacy)文化ってなんだろう?
対談型おはなし会 木村泰子とアンドウジュン』
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が収まらない状況を受けて、3月22日(日)に予定していた映画『みんなの学校』上映会、及び木村泰子さんとのお話会を、やむなく中止いたします。
また、いずれも7月19日(日)に延期する予定であることを、あわせて報告いたします。
まるで試されているかのような、毎日です。
先行きが見えない、不安な非日常が続いて、次第にみんなの心が軋み始めているのを、感じています。...
イベントを探す
愛知県近隣の人気のセミナー・研究会・勉強会
| 3/7 | 新年度のスタートダッシュを決める! 第13回黄金の三日間セミナー |
| 3/14 | 第8回先生の働き方を考えるワークライフバランスフォーラムin名古屋 |
| 3/8 | 心理カウンセラー養成ベーシック講座(2026年3月第2日曜) |
| 3/7 | 心理カウンセラー養成講座(2026年3月第1土曜集中) |
| 3/15 | 心理カウンセラー養成ベーシック講座(2026年3月第3日曜) |
関連する人気のセミナー・研究会・勉強会
| 3/28 | 絵本作家 谷口智則(たにぐち とものり)先生がきたー例会 |
| 3/14 | 生成AIフル活用で、、、学校の「データ」に強くなる! |
| 3/29 | 学び研フォーラム2026 AI時代のデザイン教育 |
| 3/7 | 交流及び共同学習シンポジウム ー 協働的学びの実現に向けて ー |
| 5/9 | 赤坂真二先生講演会(第5回授業力・学級経営力向上研修会) |
大学のセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す