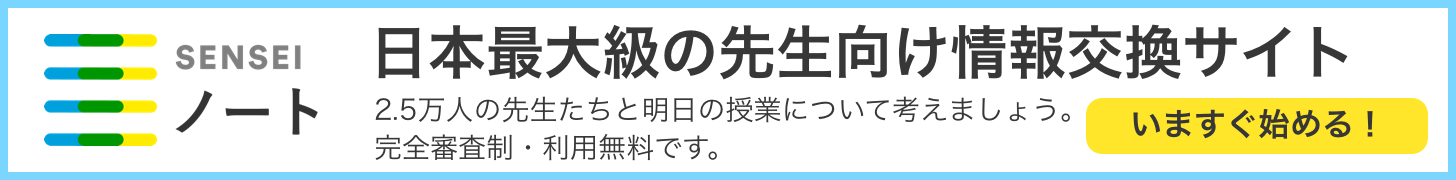| 開催日時 | 14:00 〜 17:00 |
| 定員 | 40名 |
| 会費 | 0円 |
| 場所 | その他オンライン開催 詳細は学会ホームページをご参照ください(http://hiset.jp/)。 |
研究発表「新制高等学校発足期の入学者選抜における英語の位置付けについて:広島県を例に」
河村 和也氏(県立広島大学 准教授)
【概要】筆者はこれまで、新制高等学校の入学者選抜における学力検査に英語が導入された経緯を自治体ごとに調査し、数次にわたって報告してきた。本発表は、広島県の公立高等学校を対象とするものである。
英語が初めて導入されたのは1952(昭和27)年度であり,その嚆矢となったのは宮城・福井・岡山の3県であった。この動きは全国に拡大し、6年後、つまり1958(昭和33)年度には、ほぼすべての自治体で公立高等学校の入学者選抜における学力検査に英語を課すまでにいたっている。
広島県は1953(昭和28)年度の入学者選抜から英語を取り入れ、全国で12道県に過ぎなかった英語導入自治体のひとつに名を連ねている。ただし、広島県の学力検査には他県には見られない大きな特徴があった。本発表では、その特徴を詳細に報告するとともに、新制高等学校発足期の入学者選抜が大きく揺れ動いたさまを描き出したい。
研究発表「若林俊輔の英語教育論:後期(東京外国語大学時代)の特徴」
若有 保彦氏(秋田大学 准教授)
【概要】若林俊輔(1931~2002)は1960年代~2000年代初頭に活躍した英語教育者である。若林の単著及び共著の論考,討議(対談,座談会,シンポジウム等)やインタビュー等に登場した記事は,これまで確認できたものだけで500本以上存在しているが,この数は非常に多いと言える。例えば,『英語教育fifty』(2002, 大修館書店)の付録のCDにある「特集執筆回数ランク表」によれば,若林の執筆回数は71回で過去50年間で最も多かった。また,若林の論考は目的論,教育課程論,教材論,方法論,評価論,教師・学習者論,教育史など,英語教育の様々な分野に及んでいる。
本研究は「若林俊輔の英語教育論」の全体像及びその発展の過程を明らかにすることを目的としたものである。この目的の達成のため,若林の論考及び討議,インタビュー等において登場した記事を前期,中期,後期,末期の4つの時期に分けると共に,これらをテーマ毎に分類し,各分野に関する主張はいつ頃から行われたのか,主張が変わった場合,その変化はいつから生じたのか等を調査した。
今回の発表では,若林が1980年4月から1993年3月まで勤務した東京外国語大学時代を「後期」と定義し,この時期の約250の論考,紙上討議やインタビューにおける発言を分析した結果を報告する。
イベントを探す
関連する人気のセミナー・研究会・勉強会
英語のセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す