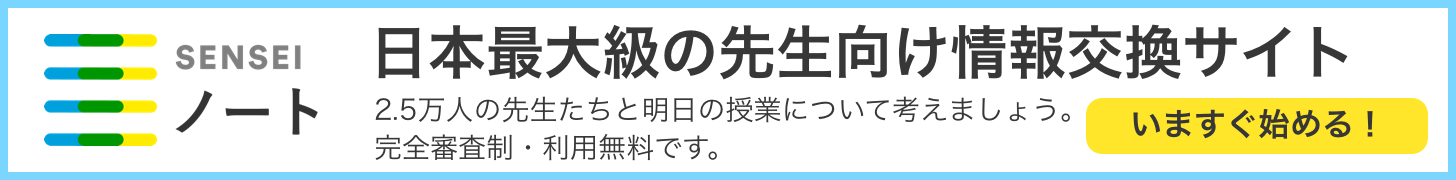| 開催日時 | 13:00 〜 16:00 |
| 定員 | 25名 |
| 会費 | 120000円 |
| 場所 | オンライン |

この度、京都芸術大学アート・コミュニケーション研究センターは主催講座「大学生と学ぶ 対話型鑑賞ファシリテーション講座」を開講します。現在、2022年度受講生(3期生)を募集しております。
今年で3年目を迎える本講座は、美術・博物館や学校現場をはじめ、ビジネスパーソンの研修や医療従事者の教育など様々な分野で広く活用されている対話型鑑賞を、その基本から実施者としてのファシリテーション技術まで、理論と実践の両面で本格的に学ぶオンライン連続講座です。
基本となる隔月開催のセミナー(7月,9月,11月,1月/全8日間)に加え、月2回の定期練習会(任意参加)での実践を通じて対話型鑑賞の理解を深め、鑑賞やファシリテーションのスキル習得を目指します。
また、本講座は講師に加え、本学で対話型鑑賞を学んでいる大学生がスタッフとして参加いたします。自らもファシリテーションのトレーニングを受け...
気になるリストに追加
1人が気になるリストに追加
イベントを探す
オンライン近隣の人気のセミナー・研究会・勉強会
関連する人気のセミナー・研究会・勉強会
ファシリテーションのセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す