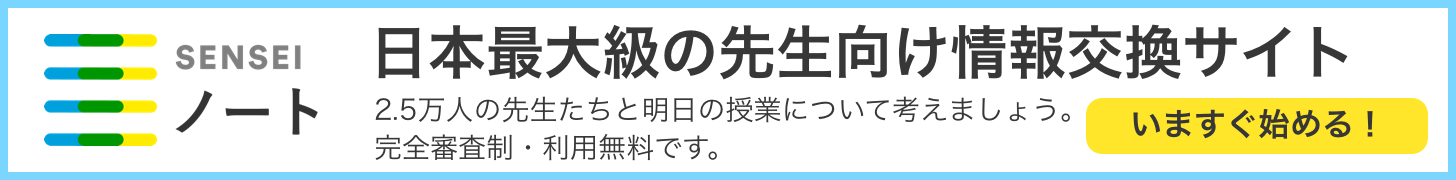| 開催日時 | 13:00 〜 15:40 |
| 定員 | 50名 |
| 会費 | 0円 |
| 場所 | 東京都 立教大学池袋キャンパス 5号館2階 5210教室 |
このイベントは終了しました
気になるリストに追加
講師:馬本 勉氏(県立広島大学教授、日本英語教育史学会副会長)
司会・対談者:熊谷 允岐(茨城大学講師、英語教育研究所特任研究員)
内容:
日本で英語学習が始まったのは今から約200年前のことです。江戸時代後期、イギリスの軍艦が長崎港に現れ、フェートン号事件と呼ばれる騒動が起こります(1808年)。その翌年、対応策として幕府が通詞(通訳兼貿易官)に英学修業を命じたことが始まりです。当時は長崎・出島でのオランダ貿易が続いており、前線で働くオランダ語に通じた「蘭通詞」が、英語のできるオランダ人から学び始めたのです。
オランダ限定であった西洋との関係は、ペリー来航に伴う開国(1854年)で英米へと広がり、英語の重要性が高まります。明治の学制や学校令により学びの制度が整っていく中、学校や独学で学ぶ人が増加し、「英学ブーム」が訪れます。当時は英米から輸入された児童向...
イベントを探す
東京都近隣の人気のセミナー・研究会・勉強会
| 2/28 | 【新しい外国語実践研究会(新外研)】 第1回発足記念学習会(対面開催) |
| 3/29 | 春の向山型算数セミナー2026 |
| 3/29 | 第23回教科書著者による小・中・高教科書指導法ワークショップ |
| 3/13 | TOSS中学社会科教員勉強会 2026.3月①(80回目) |
| 2/27 | TOSS中学社会科教員勉強会 2026.3月②(81回目) |
関連する人気のセミナー・研究会・勉強会
英語のセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す