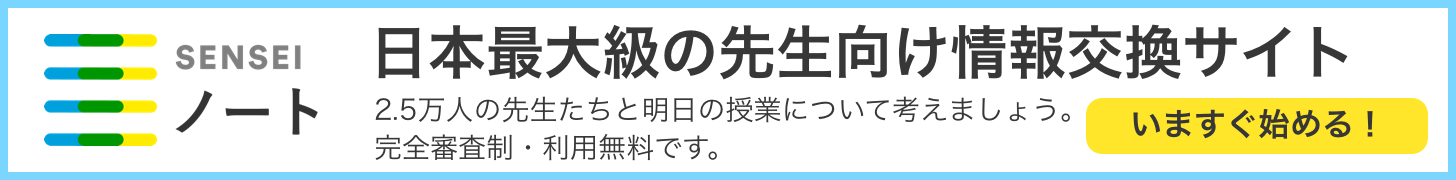自然科学研究教育センター講演会 第28回|イベント・ニュース|Research and Education Center for Natural Sciences
| 開催日時 | 16:30 |
| 場所 | 東京都 慶應義塾大学日吉キャンパス 来往舎1階 シンポジウムスペース |
| 主催 | 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター |
このイベントは終了しました
気になるリストに追加日時 2014年05月13日 ( 火 ) 16:30~18:00
会場 慶應義塾大学日吉キャンパス 来往舎1階 シンポジウムスペース
主催 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター
内容 南極の線虫とクマムシ:驚異の乾燥・凍結耐性
講師 鹿児島 浩 氏 新領域融合研究センター 特任研究員
参加費 無料(学生・塾外の方の来場歓迎)
講演要旨
南極大陸は低温で乾燥した生き物にとっての極限環境です。南極の寒さは有名ですが、同時に非常に乾燥しているということは、あまり知られていないかもしれません。南極大陸は雪と氷に覆われていて「水がない」とは思えないのですが、生き物は個体状態の水(つまり氷)を生命活動に使う事はできません。溶けない氷がどれだけ大量にあっても、生き物にとっては岩や砂と同じです。このため南極大陸は「氷の砂漠」とも言われています。このような厳しい環境にも、夏の間だけ氷が融けて出来る小川や、岩に張り付いたコケには線虫やクマムシが住んでいます。彼らは一年の大半を凍結・乾燥した状態で耐え、雪氷が溶け液体の水が得られる短い夏の間だけ成長します。
こんな厳しい環境で平気に暮らしている南極の線虫やクマムシは、何か特別な能力を持っているんじゃないかと思いませんか?(私は持っていると思います!)そこで、私はこれらの生き物を研究材料にして、驚異の乾燥・凍結耐性を担っている遺伝子を明らかにしたいと考えて研究を進めています。乾燥や凍結に耐えるための遺伝子が分かれば、将来的には食品、医療品の乾燥・凍結による長期保存に応用できたり、さらに進めば移植用の臓器や生き物の全体を低温、乾燥で長期にわたって保存できるようになるのではないかと考えています。講演では、皆さんがあまりご存じない「線虫」についての紹介から、私の研究の現状をお話したいと思います。
プロフィール
鹿児島 浩 氏
新領域融合研究センター 特任研究員
学歴:
1990年九州大学理学部生物学科卒業
1996年京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、同理学博士号取得
職歴:
1996年バーゼル大学、生物学研究所にて博士研究員として在外研究
2000年国立遺伝学研究所、生物遺伝資源情報研究室において博士研究員として勤務
2010年情報・システム研究機構、新領域融合研究センターにおいてプロジェクト特任研究員として勤務中
専門領域:
分子生物学
研究内容:
比較ゲノム解析による南極線虫の乾燥、凍結耐性遺伝子の探索
極限環境下の生物多様性-モデルサイトとしての南極湖沼
主な著書(発表論文)
Kagoshima, H. (2013) Studies on anti-desiccation and anti-freezing mechanisms in Antarctic organisms. (南極生物における凍結・乾燥耐性研究の現状) Journal of Japanese Society for Extremophiles 12 (極限環境生物学会誌12巻): 71-78
Kagoshima, H., Imura, S., Suzuki, A.C. (2013) Molecular and morphological analysis of an Antarctic tardigrade, Acutuncus antarcticus. Journal of Limnology 72(s1):15-23
Kagoshima, H., Kito, K., Aizu, T., Shin-i, T., Kanda, H., Kobayashi S., Toyoda, A., Fujiyama, A., Kohara, Y., Convey, P. and Niki, H. (2012) Multi-decadal survival of an Antarctic nematode, Plectus murrayi, in a -20°C stored moss sample. CryoLetters 33: 280-288
鹿児島浩,小原雄治 (2007) 多様な線虫のシステム比較 -モデル生物C. elegansから極限環境線虫まで-.
伊藤隆司,小原雄治,榊佳之,辻省次(編)実験医学 Vol.25 No.2(増刊)ゲノム情報と生命現象の統合的理解.羊土社,東京.pp 136-142
センター主催のシンポジウム・講演会について
当センターの活動の一環として、シンポジウム・講演会を年3~4回程度開催しています。その目的は、多分野にまたがる自然科学の相互理解を深め、研究の推進と教育の質の向上を図ることにあります。参加費は無料です。聴講の対象も制限はありません。特に指定のない場合、事前申込は不要です。ただし、取材の場合は事前に許可を取って下さい。
天災・交通事情など予期せぬ事態により変更・中止となる場合がございます。
その場合、本ウェブサイトで告知しますので、事前にご確認下さい。
問合せ先:慶應義塾大学 自然科学研究教育センター 事務局 (日吉キャンパス来往舎内)
〒223-8521 横浜市港北区日吉 4-1-1
Tel: 045-566-1111(直通) 045-563-1111(代表) 内線 33016
office@sci.keio.ac.jp
イベントを探す
東京都近隣の人気のセミナー・研究会・勉強会
| 3/28 | 「学級づくり」を考える会 |
| 2/20 | 成城学園初等学校・第43回教育改造研究会 |
| 2/22 | 教師のキャリアを考える会 |
| 2/15 | 中身のない『働き方改革』後にも生き残る教師(小、中、高)になるために:学びをつくる会第30回大集会 |
| 2/23 | くもん出版「みんなの笑チャレ!!!」出版記念サイン会&ミニワークショップ |
生物のセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す