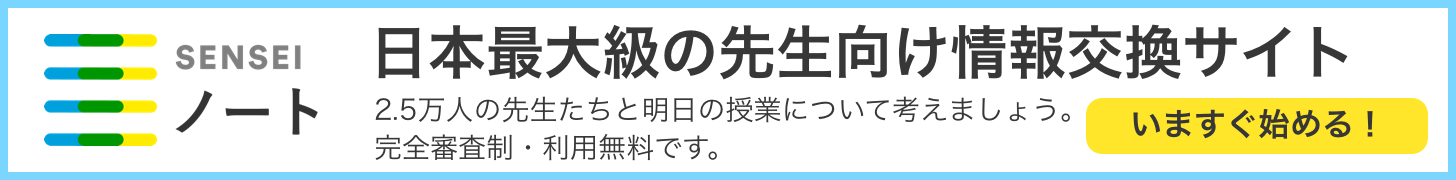| 開催日時 | |
| 会費 | 7,000円(税込)円 |
| 場所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 上大岡会場<ウィリング横浜> |
| 主催 | 神奈川LD協会 |
このイベントは終了しました
気になるリストに追加【神奈川LD協会 第1回わらしべ実践交流集会】
現場で日々汗をかいて働く支援者の、支援者による、支援者のための研修会をコンセプトに、実践発表や教材展示など盛りだくさんの新しいタイプの研修会です。
ごあいさつ
いつも神奈川LD協会の研修会にご参加いただき、ありがとうございます。これまで当協会では、主に大学の教員や研究者に講師を依頼し、支援者の皆さんが参加者という一方向教示型の研修を行って参りました。
しかし、現場の質が高まり、支援者層の厚みも増してくる中で、発達障害や特別支援教育、不登校・ひきこもり、子ども虐待等の分野で豊かな実践力を身につけていらっしゃる方々も増えてきています。
そこで今回、「現場で日々汗をかいて働く支援者の、支援者による、支援者のための研修会」をコンセプトに、皆さんから日々の実践を発表いただき、多くの仲間と膝を交えることのできる研修会を開きたいと考えました。学...
イベントを探す
神奈川県近隣の人気のセミナー・研究会・勉強会
| 3/27 | 高校古典を知的に楽しく 「へぇ~」「おお~」を引き出す授業の工夫5選 |
| 3/8 | 3/8(日) 子どもの救命救急法 国際資格 EFR-CFC 取得講座 |
| 4/18 | 4/18(土) 子どもの救命救急法 国際資格 EFR-CFC 取得講座 |
| 5/2 | 5/2(土) 子どもの救命救急法 国際資格 EFR-CFC 取得講座 |
| 3/15 | 新英語教育研究会 神奈川支部 3月例会(オンライン) |
関連する人気のセミナー・研究会・勉強会
| 3/29 | 春の向山型算数セミナー2026 |
| 3/1 | 【3月1日】石坂BEGINNERSセミナー2025/26 Second season 〜価値ある教師であるための学習会〜 |
| 3/22 | 2026.0322KTO春の大研修会 |
| 3/1 | <入場も研修会参加も無料>「できた!」につながるヒントを見つけよう!【できるびよりフェスタ2026】 |
| 3/1 | 第5回みんなの「自力読み」セミナー(対面) |
小学校のセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す