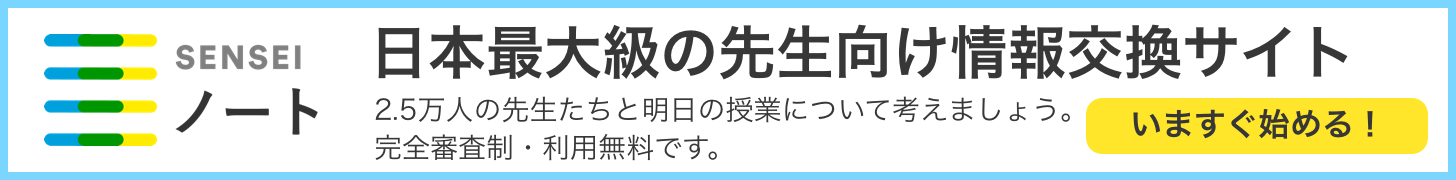| 開催日時 | 13:20 〜 16:40 |
| 場所 | 東京都千代田区外神田5丁目3-10 株式会社ナリカ2F実験室 |
このイベントは終了しました
気になるリストに追加
NSAに関しては下記のサイトをご覧ください。
https://www.rika.com/nsa
講師:桑子研
【実験室のみの講座となります】
※学生の方は、オンライン学生チケットを選び大学発行のメールアドレスを登録してください(例ac.jpのメールアドレス)。
A講座 13:20~14:50「光」
光の反射や屈折といった現象を、ただ教科書で説明するだけでは生徒の心に残りません。そこで今回は、理科嫌いの生徒も思わず前のめりになるような、仕掛け満載の“光”実験を紹介します。光の三原色や色の三原色といった内容も織り交ぜながら、「見えるってどういうこと?」という根源的な問いにアプローチしていきましょう。
① 導入で心をつかむ!カード型ミラーを使った光の遊び
ミラーに映った像が現実とどう違うのか? 左右反転や奥行きの感覚を試す簡単な遊びを通じて、光の進み方に自...
イベントを探す
東京都近隣の人気のセミナー・研究会・勉強会
| 2/14 | 第2回道徳科ウィンターセミナー(日本道徳科教育学研究学会) |
| 2/7 | 令和7年度東京学芸大学附属世田谷小学校研究発表会 |
| 3/7 | 理論に基づく実践事例を通して日本の教育の未来を考える「主体的学びを考えるシンポジウム ~自己調整学習理論に基づく教育デザインのあり方~」 |
| 2/14 | ALL飯田清美セミナー |
| 2/21 | 第1回 アドベンチャーと学びの未来フォーラム ー怒らない指導から学びの環境を問い直すー |
関連する人気のセミナー・研究会・勉強会
| 4/11 | 中谷康博先生の理科実験教室 IN 石橋南小申し込みフォーム(対面のみ) |
| 3/28 | 春フェス 糸魚川会場 |
| 5/10 | 第3回TOSS春の教師フェス 医教連携~発達障がい対応レベルアップセミナー |
| 3/20 | 1,2,3年生の授業の基礎・基本が学べる! 春の教師力アップフェス! |
| 3/28 | たのしい授業入門講座 |
実験のセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す