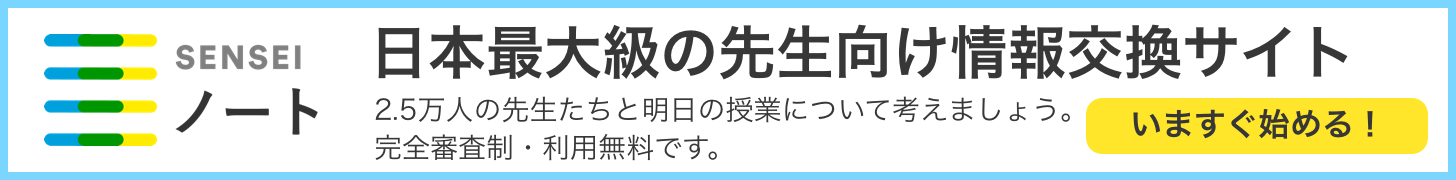| 開催日時 | 13:00 〜 18:00 |
| 定員 | 200名 |
| 会費 | 3000円 |
| 場所 | 東京都渋谷区 国立オリンピック記念青少年総合センター とオンラインのハイブリッド開催 |
このイベントは終了しました
気になるリストに追加
後半の講演内容に詳しい概要を6月27日に加えました!
NPO法人理科カリキュラムを考える会 2025年度夏季シンポジウム
素朴概念を踏まえた授業作りに挑戦しよう
ー英ヨーク大・素朴概念研究の簡易翻訳を参考にー
2025年6月29日(日) 13:00〜18:00【ハイブリッド開催】
主 催:NPO法人理科カリキュラムを考える会 https://rikakari.jp/
会 場:国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟3階309室
東京都渋谷区代々木神園町3−1(オンラインからも参加できます)
対 象:小・中・高・大の理科教育に携わる方、教育ジャーナリスト、一般
参加費:一般3,000円 本会会員2,000円 学生1,000円 定員:対面80名+オンライン120名
申込み:右のURLから https://rikakari20250629.peatix...
イベントを探す
東京都近隣の人気のセミナー・研究会・勉強会
| 2/14 | 第2回道徳科ウィンターセミナー(日本道徳科教育学研究学会) |
| 2/7 | 令和7年度東京学芸大学附属世田谷小学校研究発表会 |
| 3/7 | 理論に基づく実践事例を通して日本の教育の未来を考える「主体的学びを考えるシンポジウム ~自己調整学習理論に基づく教育デザインのあり方~」 |
| 2/14 | ALL飯田清美セミナー |
| 2/21 | 第1回 アドベンチャーと学びの未来フォーラム ー怒らない指導から学びの環境を問い直すー |
関連する人気のセミナー・研究会・勉強会
理科のセミナー・研究会・勉強会を別の地域から探す
人気のキーワードから探す